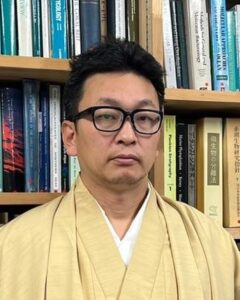|
プログラムの特徴
・アート思考を通じて、自分自身の感性や問いに気づくきっかけをつくる。
・“土”や“菌”といった素材との出会いから、暮らしや社会とのつながりを身体的に感じとる。
・社会課題を構造的に捉える「システミックデザイン」の思考法を学び、視点のレイヤーを増やす。
・発酵、建築、ジビエ、微生物など、多分野にまたがる知や実践を通じて、循環型の暮らしを考える。
・対話やフィールドワークを重ねながら、“暮らしの再構築”を可視化し、未来の社会像を描き出す。
プログラムの目的
・自分が本当にやりたいことに気づき、自らの問いを“自分ごと”として深めていく。
・サステナビリティを単なる知識としてではなく、素材・場所・他者との関係の中で体感的に理解する。
・社会や自然に内在する課題の構造を見つめ、ファクトと感性の両面から“なぜ”を掘り下げる。
・一生をかけてでも取り組みたい“問い”を見出し、それを原点にしたビジョンや行動の芽を育てる。
・こうしたプロセスを通じて、未来の暮らしや社会のあり方を、自らの手で再構築する力を育む。
スケジュール
|
日 時 |
タイトル |
| 1 |
7/6(日)
13:00-17:00 |
土で思考する! 〜 土の感覚から表出するアート思考 〜 |
| 2 |
7/12(土)
10:00-12:00 |
社会課題を構造で捉える - システミックデザイン入門 |
| 3 |
7/12 (土)
13:00-17:00 |
生きた現場から学ぶ - 問いを育てるケーススタディ |
| 4 |
7/19(土)-20(日)
一泊二日 |
フィールドワーク
素材と命にふれ、自ら未来の暮らしを編みなおす — ビジョンを描く旅へ |
| 5 |
7/27(日)
13:00-17:00 |
メンタリング/システミックデザイン 〜 システムへの介入戦略を検討する 〜 |
| 6 |
8/2(土)
13:00-17:00 |
最終発表 |
講師紹介
 |
美術家/kumagusuku代表/京都芸術大学 美術工芸学科 専任講師 矢津 吉隆
1980年大阪生まれ。京都市立芸術大学美術科彫刻専攻卒業。京都芸術大学美術工芸学科専任講師、ウルトラファクトリープロジェクトアーティスト。京都を拠点に美術家として活動。また、作家活動と並行して宿泊型アートスペースkumagusukuのプロジェクトを開始、瀬戸内国際芸術祭2013醤の郷+坂手港プロジェクトに参加したのち、京都にてKYOTO ART HOSTEL kumagusuku を開業。主な展覧会に「青森EARTH 2016 根と路」青森県立美術館(2016)、個展「umbra」Takuro Someya Contemporary Art (2011)など。また、アーティストのアトリエから出る廃材を流通させるプロジェクト「副産物産店」やアート思考を学ぶ社会人向けのアート塾「BASE ART CAMP」のプログラムディレクターを務めるなど活動は多岐にわたる。
|
 |
京都工芸繊維大学 未来デザイン・工学機構 准教授 水内 智英
デザイン研究者・プロジェクトディレクター / 京都工芸繊維大学未来デザイン・工学機構 准教授 / 博士
武蔵野美術大学基礎デザイン学科で基礎デザイン学を、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ大学院MA in Design Futuresでメタデザインを学ぶ。京都工芸繊維大学で博士号(学術)を取得。英国のクリエイティブエージェンシー勤務、名古屋芸術大学准教授などを経て現職。デザインの在り方それ自体を問いなおすための研究に取り組み、優先社会イノベーションやシステミックデザイン、主体との協働デザインに関する研究活動、実践的なプロジェクトを行う。著書に「ヴィジュアルリテラシースタディーズ(共著)」、「多元世界へ向けたデザイン(共監訳)」など。NPO法人issue+designクリエイティブディレクター/理事、基礎デザイン学会理事。
|

|
相模女子大学大学院社会起業研究科/学芸学部 特任教授 依田 真美
20年以上に渡り外資系金融機関や格付機関で証券アナリストとして日本、韓国、中国の大手事業会社および公的部門、自治体の格付けを担当する。2009年にかねてから関心のあった地域活性化に取り組むため退職し、北海道大学大学院国際広報メディア観光学院博士後期課程に進学。2017年より相模女子大学学芸学部に勤務、大学院社会起業研究科の立ち上げに参画。
MITスローン経営大学院修了、修士(経営学)、北海道大学大学院国際メディア・観光学院博士後期課程修了、博士(観光学)。
|
ゲストスピーカー紹介
|

|
元京都大学大学院農学研究科 准教授 高柳 敦
東京生まれ、大学入学以降京都在住。1980年代からニホンカモシカによる農林業被害問題に取り組む。現在は、シカ、イノシシ、クマ、サルなどの野生動物による被害問題の解決のための研究を行っている。特に、被害を防ぐための防護方法について研究し、近畿を中心に各所で防護柵の設計、施工、維持管理を実際に行い、また、指導している。防護柵による防護の実地研修も行っている。2015年からは大阪府猟友会との連携も進めている。野生動物被害問題の社会的側面、狩猟制度、野生動物利用の在り方などについても取り組み、野生動物の存在が組み込まれた社会と野生動物文化の形成をめざす。食害防除ボランティア「かもしかの会関西」代表。専門は野生動物保全学
|
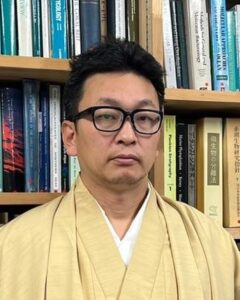
|
㈱Seed Bank 代表取締役/農学博士/微細藻類ハンター 石井 健一郎
略歴:
2012年 京都大学大学院農学研究科 博士号取得
2012~2014年 同農学研究科研究員
2014~2018年 京都大学大学院地球環境学堂 研究員
2018~2022年 京都大学大学院 人間・環境学研究科 研究員
2015年2月 京都大学起業家養成プログラム(GTEP)優勝
2017年2月 株式会社Seed Bank設立
|

|
名古屋大学 未来社会創造機構 脱炭素社会創造センター イノベーション部門 特任講師 谷村 あゆみ
総合研究大学院大学にて博士(理学)の学位を取得。企業勤務などを経て、2022年4月から2024年2月まで京都大学産官学連携本部の特定助教として勤務。2024年3月より現職。学位取得までの専門は物理化学だったが、研究の過程で微生物の奥深さに魅了され、分野を大きく転換。現在は応用微生物学を専門とし、産業応用を視野に入れた研究に取り組んでいる。
|
企画設計・運営管理
中原 有紀子(京都大学 成長戦略本部 統括事業部 エコシステム構築領域 イノベーション マネジメント サイエンス部 研究員)

詳細はこちら
|